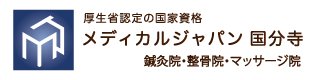BLOG・NEWS
- TOP >
- コラム
-
仕事モードに切り替える!朝の“姿勢スイッチ”ストレッチ
今回は「【出勤5分前】仕事モードに切り替える!朝の“姿勢スイッチ”ストレッチ」について、ご紹介します!
「会社に着いたけど、なんだかボーっとして頭が働かない…」
「座ってすぐに仕事に入ると、集中できず効率が悪い…」
「朝から体が重だるく、やる気が出ない…」そんなお悩み、ありませんか?
実はその“やる気の出なさ”や“集中力の低下”、姿勢と深く関係しているのです。
【出勤前5分】朝の“姿勢スイッチ”ストレッチで体をリセット!
たった5分でできる、出勤直後におすすめのセルフケアをご紹介します。
体の軸を整え、深い呼吸とともにスイッチを入れましょう!✅ 所要時間:約5分
1. 骨盤ゆらし(約1分)
椅子に浅く腰かけ、背筋を軽く伸ばします。
両手を腰に当て、骨盤を前後にゆっくりと動かします。→ 重心が後ろに傾いていると猫背に。骨盤をやや前に起こす意識で、自然と背筋が整います。
2. 肩甲骨ほぐし(30秒×2回)
両手を肩に添え、肘で大きな円を描くように前まわし・後ろまわしを行います。→ 肩周りの緊張がゆるみ、胸が開いて呼吸がしやすくなります。
3. 背骨ストレッチ(約1分)
両手を頭の上で組み、そのまま天井に向かってぐーっと伸ばします。
かかとに軽く体重を感じ、背骨がまっすぐ伸びていくのを意識しましょう。→ 姿勢の軸が整い、頭がすっきりしやすくなります。
4. 深呼吸で自律神経リセット(30秒〜1分)
鼻から4秒吸い、口から8秒かけて吐く。これを3回。→ 吸う時にお腹がふくらみ、吐く時にゆっくりしぼむよう意識すると、副交感神経が優位に働きリラックス&集中モードへ切り替え!
姿勢を整えると、朝から“やる気スイッチ”が入る!
姿勢を整えることで、
✅ 呼吸が深くなり、脳がクリアに
✅ 血流が促進され、体が目覚める
✅ 気分も前向きになり、仕事モードに!当院では、鍼灸・整体・マッサージを組み合わせた総合的なアプローチで、症状の根本改善をサポートしています。
慢性的な症状や再発を防ぐためのセルフケア指導も行っていますので、気になる方はお気軽にご相談ください。 -
【年末年始のお知らせ】
【年末年始のお知らせ】
12月30日~1月5日まで休診になります。1月6日より通常診療になります。急性の痛みでお困りでしたら
メディカルジャパン新宿院・立川院は年中無休で診療しています。 -
【腰痛持ち必見!】原因は“もも前”の硬さかも?体の前側をゆるめて腰が軽くなるセルフケア
今回は「【腰痛持ち必見!】原因は“もも前”の硬さかも?体の前側をゆるめて腰が軽くなるセルフケア」について、ご紹介します!
「長時間座っていると腰が痛くなる…」
「慢性的な腰の重だるさが続いている…」
「腰を揉んでもよくならない…」そんなお悩み、ありませんか?
実はその腰痛、「もも前(大腿四頭筋)」の硬さが関係しているかもしれません。
もも前が硬くなると骨盤が前に引っ張られ、反り腰の姿勢になりやすくなります。反り腰は腰への負担が大きく、腰痛の大きな原因のひとつなのです。
腰痛と“もも前の硬さ”の関係とは?
腰痛=腰まわりだけの問題だと思われがちですが、実際には下半身の筋肉バランスも大きく関係しています。とくに注目すべきなのが、以下のようなポイントです。・長時間の座り姿勢でもも前の筋肉が縮みっぱなしになる
・歩かない生活で太ももの柔軟性が失われている
・もも前が骨盤を前に引っ張り、反り腰状態に
・結果、腰の筋肉が常に緊張して負担が増大
つまり、腰ばかり揉んでも根本改善にならないのは、下半身に根本原因があるケースが多いからなんです。
もも前の硬さを改善!腰が軽くなるストレッチ習慣【3分ケア】
✅ やり方(所要時間:約3分)1. 正しい姿勢で立つ
壁に背中を軽くつけて立ち、背筋をまっすぐに整えます。骨盤が前に倒れすぎていないかを意識。2. 片脚ずつ、もも前ストレッチ(左右30秒ずつ)
足を肩幅に開いて立ち、片脚を後ろに曲げて足首を手で持ちます(片脚バランス)膝を軽く後ろに引き、もも前がじんわり伸びる感覚を大切に
無理に引っ張らず、呼吸を止めずに行いましょう
※バランスが不安定な場合は、壁や椅子につかまりながら行ってください。
3. 太ももほぐし(30秒)
床に座って、もも前を軽く拳でトントン叩きます呼吸に合わせてリズミカルに、筋肉を緩めていきます
4. 最後に骨盤リセットの深呼吸(3回)
椅子に座って背筋を伸ばし、鼻から息を吸って、口からゆっくり吐きます呼吸に合わせて骨盤の位置が自然に整っていく感覚を味わいましょう
腰痛は「腰が原因」とは限りません。体の前側(特にもも前)をケアすることが、腰への負担を減らす大きな鍵になります。
デスクワークや運動不足で硬くなりがちな太ももを、毎日のちょっとした習慣でほぐしていきましょう。
当院では、鍼灸・整体・マッサージを組み合わせた総合的なアプローチで、腰痛の根本改善をサポートしています。
慢性的な症状や再発を防ぐためのセルフケア指導も行っていますので、気になる方はお気軽にご相談ください。
-
【巻き肩&首こり】姿勢を整えてスッキリリセット
今回は「【巻き肩&首こり】姿勢を整えてスッキリリセット」について、ご紹介します!
「最近、肩が内側に入りがち…」
「首がいつも張っている感じがする」
「デスクワークのせいか、姿勢がどんどん悪くなってきた…」そんなお悩み、ありませんか?
それ、巻き肩や首こりが原因かもしれません。巻き肩・首こりとは?
巻き肩とは、肩が前に巻き込まれたように内側へ入ってしまう状態のこと。
長時間のスマートフォン操作やパソコン作業など、前かがみの姿勢を続けることで、胸の筋肉(大胸筋・小胸筋)が縮こまり、背中の筋肉が引っ張られてしまいます。この状態が続くと、自然と首や肩に負担がかかり、「首こり」や「肩こり」を引き起こします。
スマホ首が引き起こす不調
巻き肩・首こりによる体の不調
肩や首の張り・こりの慢性化・頭痛や目の疲れ
・猫背・姿勢の悪化
・呼吸の浅さ・疲れやすさ
・自律神経の乱れ(不眠・イライラ)
特に、胸の筋肉が硬くなって肩甲骨の動きが悪くなり、僧帽筋や肩甲挙筋などの負担が増すことで、悪循環に陥ってしまいます。
巻き肩&首こり対策ストレッチ【胸開きストレッチ】
✅ やり方壁の横に立ち、肘を90度に曲げて前腕を壁につける
そのまま体を少し前に出し、胸をぐっと開く
胸の前側が伸びているのを感じながら、深呼吸しつつ15秒キープ
反対側も同様に行う
→ 朝と夜、左右1セットずつを目安に。
背中が丸くならないよう注意しながら、ゆっくりと行いましょう。当院では、鍼灸・整体・マッサージを組み合わせたトータルケアを行なっています。
肩こりや腰痛、美容ケア、スポーツケアなど、幅広いお悩みに対応しております。 -
【スマホ首】日常の悪習慣が体に与える影響と改善策
今回は「【スマホ首】日常の悪習慣が体に与える影響と改善策」について、ご紹介します!
「最近、首や肩がずっと重い…」
「頭痛や眼精疲労がつらい」
「なんだか姿勢が悪くなった気がする」そんな不調、感じていませんか?
もしかしたらその原因、「スマホ首」かもしれません。
スマホ首とは?
スマホ首(ストレートネック)とは、本来カーブしているはずの首の骨(頚椎)がまっすぐになってしまう状態のこと。
スマートフォンやPCの長時間使用によって、頭が前に突き出た姿勢を続けることで起こります。現代人に増えているこの状態、実は見た目だけでなく体にも大きな影響を与えています。
スマホ首が引き起こす不調
肩こり・首こりの慢性化頭痛やめまい
自律神経の乱れ(不眠・イライラ)
猫背や巻き肩などの姿勢悪化
集中力の低下や目の疲れ
呼吸の浅さ・代謝の低下
特に、首の前側にある胸鎖乳突筋や、後ろ側の僧帽筋・後頭下筋群などが緊張することで、首の動きが制限され、血流やリンパの流れも悪化してしまいます。
🔹ストレートネック対策ストレッチ【胸鎖乳突筋リリース】
椅子に座り、姿勢を正す首を右に傾け、左手で鎖骨のあたりを軽く押さえる
そのままゆっくりと天井を見上げ、胸を開く
左側の首が伸びていることを感じながら、10秒キープ
反対側も同様に
→ 朝・夜2セットずつが目安。呼吸を止めず、ゆったりと行いましょう。
当院では、首や肩の深層筋へのアプローチに加え、自律神経を整えるツボ刺激、猫背や巻き肩の調整など、
スマホ首の根本原因に合わせたオーダーメイド施術を提供しています。