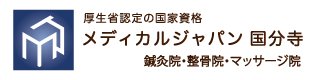BLOG・NEWS
- TOP >
- コラム
-
気圧の変化で不調になりやすい人へ!自律神経を整えるセルフケア習慣
今回は「気圧の変化で不調になりやすい人へ!自律神経を整えるセルフケア習慣」について、ご紹介します!🌦
「最近なんだか、だるい…」
「頭が重くて集中できない」
「気圧が下がると気分まで落ち込む」そんなお悩み、もしかしたら**“自律神経の乱れ”**が原因かもしれません。
気圧の変化が体に与える影響とは?
人の体は、日々変わる気温や湿度、そして「気圧」にも敏感に反応しています。
特に、低気圧が続くと交感神経と副交感神経のバランスが崩れやすくなり、自律神経が乱れることがあるのです。👇この自律神経の乱れによって、以下のような不調が現れやすくなります。
・頭痛、めまい、吐き気
・首こり・肩こり
・睡眠の質の低下
・疲労感、集中力の低下
・気分の落ち込み、不安感
つまり、気圧の変化が多い季節には、「自律神経ケア」がとても重要なのです。
自律神経を整えるセルフケア習慣
当院では、気圧による不調を和らげるために、以下のようなセルフケアをおすすめしています。✅ 深呼吸と姿勢のリセット
自律神経は「呼吸」と密接な関係があります。
ゆったりとした深呼吸を意識することで、副交感神経が優位になり、リラックス効果が期待できます。また、姿勢の乱れは自律神経のバランスに悪影響を与えるため、背筋を伸ばし、首や肩に力を入れすぎない姿勢を心がけましょう。
✅ 軽いストレッチで血流促進
気圧の変化で体が重だるく感じるときは、首・肩・背中周りのストレッチがおすすめです。
筋肉の緊張がゆるむことで、血流が促進され、自律神経のバランスも整いやすくなります。✅ 首や頭のマッサージでリラックス
特におすすめなのが、後頭部~首のつけ根にかけての優しいマッサージ。
ここには自律神経の働きに関わる重要なポイントが集中しています。当院では、鍼灸・整体・マッサージを組み合わせたトータルケアを行なっています。
肩こりや腰痛、美容ケア、スポーツケアなど、幅広いお悩みに対応しております。 -
慢性腰痛にサヨナラ!腸腰筋を柔らかくするストレッチ法
今回は「慢性腰痛にサヨナラ!腸腰筋を柔らかくするストレッチ法」について、ご紹介します!
「いつも腰が重だるい…」
「長時間座っていると腰が痛くなる」
「朝起きると腰が固まっている感じがする」そんな腰の不調、実は**腸腰筋(ちょうようきん)**が関係しているかもしれません!
腸腰筋ってなに?腰痛との深〜い関係
腸腰筋とは、腰椎から骨盤・太ももをつなぐ深層筋(インナーマッスル)です。
座りっぱなしや運動不足が続くと、腸腰筋が硬くなり、骨盤が前傾して腰に過度な負担がかかるようになります。その結果…
・腰の可動域が狭くなる
・慢性的な腰痛が続く
・姿勢が崩れて疲れやすくなる
といった不調につながるのです。
腸腰筋を柔らかくするためのストレッチ法
腸腰筋の柔軟性を取り戻すことで、腰への負担を軽減し、根本的な改善を目指せます。
以下のストレッチを、1日3分から始めてみましょう!✅おすすめストレッチ:腸腰筋リリース
・片膝立ちの姿勢をとります
→ 右足を前に出し、左膝を床につけます。・骨盤を前にスライドさせるように体重をかけます
→ 背筋を伸ばしたまま、腰を前に押し出すイメージで。・左の股関節前面が伸びているのを感じましょう
→ そのまま15〜30秒キープし、反対側も同様に行います。当院では、鍼灸・整体・マッサージを組み合わせたトータルケアを行なっています。
肩こりや腰痛、美容ケア、スポーツケアなど、幅広いお悩みに対応しております。 -
お尻の硬さが腰痛を引き起こす? 大臀筋ほぐしで辛い腰痛へおさらば!
お尻の硬さが腰痛を引き起こす?
大臀筋ほぐしで辛い腰痛へおさらば!「長時間座っていると腰が重だるい…💺」
「朝起きると腰が痛い🌅」
「ストレッチしてもなかなか改善しない🤸♂️」そんな悩み、もしかしたら
“お尻の筋肉の硬さ”が原因かもしれません!😱💡お尻の筋肉と腰痛の意外な関係とは?
腰痛といえば「腰の筋肉」に原因があると思いがちですが、
実は**お尻の筋肉=大臀筋(だいでんきん)**が大きく関係しています!大臀筋は、体の中でもっとも大きな筋肉のひとつで
・身体を支える
・骨盤の安定
・歩く・立つ・座るといった動作の補助
など、日常の動きに深く関わっているんです!
ところが…
📌 デスクワークやスマホ使用で座りっぱなしが続くと、大臀筋が硬くなりやすい
📌 大臀筋が硬くなると骨盤が引っ張られ、姿勢が崩れやすくなる
📌 結果、腰に負担がかかり、慢性的な腰痛に…つまり…
「お尻の筋肉の柔らかさ」こそが、腰痛予防・改善のカギ!👐まずは、大臀筋をゆるめるケアから!
当院では、鍼灸・整体・マッサージを組み合わせたトータルケアで、
硬くなった大臀筋を的確にほぐし
骨盤のバランスを整えるサポートを行っていますさらに👇
✅ 腰痛の原因になりやすい姿勢のクセや
✅ 筋力バランスのチェックも行い、
根本からの改善を目指します💯 -
眠りの質UP!枕の高さがカギを握る、快適睡眠の秘訣とは?
今回は「眠りの質UP!枕の高さがカギを握る、快適睡眠の秘訣とは?」について、ご紹介します!
「朝起きても疲れが取れない…」
「肩や首が痛くて目が覚める」
「寝つきが悪く、何度も目が覚める」そんな悩み、もしかしたら**“枕の高さ”が合っていない**のが原因かもしれません!
枕の高さが睡眠に与える影響とは?
人は眠っている間も無意識に姿勢を調整しながら休んでいます。
その中で枕は、「首・肩・背骨のラインを自然に保つ」ための重要な役割を果たします。ところが…
・高すぎる枕は、首が前に傾き、気道が圧迫されていびきや無呼吸の原因に
・低すぎる枕は、首の筋肉が緊張し、肩こりや首こりの原因に
・合わない枕は、睡眠の質を低下させ、深い眠りが得られないことも…つまり、「自分に合った枕の高さ」が、快適な睡眠には欠かせないのです。
当院では、鍼灸・整体・マッサージを組み合わせたトータルケアで、
首・肩まわりの緊張をゆるめ、呼吸や自律神経を整えるサポートを行っています。さらに、枕の正しい位置や高さを測定する「枕診断」も実施中!
お一人おひとりの体格や寝姿勢に合わせた枕選びのアドバイスも可能です。 -
【立ちっぱなしでむくみがひどい?原因と効果的な予防・解消法を徹底解説】
今回は「【立ちっぱなしでむくみがひどい?原因と効果的な予防・解消法を徹底解説】について、ご紹介します!
「一日中立ち仕事で足がパンパン…」
「夕方になると靴がきつく感じる」
「立っているだけでだるさや重さを感じる」そんな悩み、実は**立ちっぱなしによる“むくみ”が原因かもしれません!
🦵立ちっぱなしで起こる「むくみ」とは?
長時間の立ち仕事や立ち続ける状態は、足やふくらはぎに負担がかかります。
血液やリンパの流れが滞りやすくなり、水分や老廃物が足に溜まってしまうことでむくみが生じます。その結果…
・血流やリンパの流れが悪くなる
・筋肉の疲労や硬直が進む
・自律神経のバランスが乱れることも
これらが複合して、足のだるさや重さ、痛みを引き起こすのです。
💡立ちっぱなしによるむくみを防ぐポイントは?
むくみの予防と解消には、「血流促進」と「筋肉ケア」がとても大切です!✅ こまめに足を動かす
→ つま先立ちやかかと上げ運動でふくらはぎの筋肉を刺激し、ポンプ作用を高めましょう。✅ 足を高くして休む
→ 仕事の合間や帰宅後に、足を心臓より高い位置にあげて血液循環を促します。✅ 水分・塩分のバランスに注意
→ 適切な水分補給は必要ですが、塩分の摂りすぎはむくみの原因に。バランスを意識しましょう。✅ 弾性ストッキングやサポーターを活用
→ 血流をサポートし、むくみの軽減に効果的です。✅ 入浴やマッサージで筋肉をほぐす
→ 血行を促進し、疲労回復とむくみ解消に役立ちます。当院では、鍼灸・整体・マッサージを組み合わせたトータルケアを行なっています。
肩こりや腰痛、美容ケア、スポーツケアなど、幅広いお悩みに対応しております。